ご存じですか?民生委員・児童委員

核家族化や少子高齢化の進行、ライフスタイルや価値観の多様化などにより、地域のつながりが希薄化している中、地域を見守り支援する「民生委員・児童委員」の存在はますます重要になってきています。
今回は、地域福祉の担い手である民生委員・児童委員の活動などについて、府中市民生委員児童委員協議会会長の藤原さんにお話を伺いました。
藤原会長にインタビュー ~「ありがとう」の言葉と人とのつながりが財産~
民生委員・児童委員となったきっかけを教えてください。

府中市民生委員児童委員協議会会長
藤原洋子さん
47歳の時に「民生委員・児童委員さんになってみませんか?」とお話がありました。私よりふさわしい人がいるのではと迷いましたが、主人の「やってみればいいよ」という言葉と、学生時代に学んだ「他者のために支援ができる人になりなさい」という教えに後押しされて引き受けました。
実は最初は、民生委員・児童委員という言葉すら知らなかったのですが、1年くらいかけて自分の担当地域を訪問して回り、どんな方が住んでいるのかを知ることから始めました。ありがたいことに、鵜飼町は先輩方が築いた活動の基盤があったので、やりやすかったですね。しかし、委員になってすぐに生活保護を受ける方の支援をすることになった時はびっくりしましたよ。何も分からない中、無我夢中で取り組んだのを今でもよく覚えています。
普段どんな活動をされているのですか?
地域の皆さんのお宅を訪問し、困っていることや心配ごとはないかなど、話を聞いています。相談内容に応じて、行政や社協などの関係機関につなぎ、必要な支援を受けられるようサポートするのも民生委員・児童委員の役割ですね。地域の方と顔を合わせてお話しし、信頼関係を築くことを活動の基本にしています。

見守り(訪問)活動

地域包括支援センターなど関係機関との連携
地域の課題について考えをお聞かせください。
高齢化や核家族化などで、どこの地域も人間関係が希薄になり、つながりが薄いですよね。困っている人がいたら隣近所で助け合おう、そんな気持ちや愛情を持つことが大切なのに、今の日本はこれが欠落していると思います。このような状況では、悩みを抱えていても支援してくれる人がいない人、自分から助けを求めることができない人が孤立してしまいます。そんな人たちを見つけて支援する、そのための民生委員・児童委員だと考えています。そして、地域課題を掘り下げ、人と人をつなぐ仕組みづくりが必要だと思っています。
「人と人をつなぐ仕組みづくり」。そのためにさまざまな活動をされているのだとか。
2年前に県の地域まるごと相談見守り推進事業を受けて、「まるごと鵜飼」という愛称で活動を行っています。町内会やコミュニティースクールなどと連携し、三世代をつなぐイベントとして始めたのが、楽しく学ぶ防災活動です。防災かまどベンチでの炊き出し体験やゲームを通じて、防災について親子で学びます。この活動のキーワードは、「みんながいきいきと楽しく過ごせる環境がある」、そして「みんなが入り込める隙間づくり」。子どもたちは楽しく体を動かして喜んでくれますし、地域の皆さんも、竹を使ってご飯を炊く、広報誌やイベントで使うぬいぐるみ作りなど、得意なことを活用した役割があるので活気づくんですよね。何より、この活動を通じて、皆さんが顔見知りになり、仲良くなる。困った時に協力し合える地域のつながりができていると感じています。

三世代をつなぐ防災活動

サロン活動・フラワーアレンジメントの集い
やりがいはどんなところですか?
生活保護を受けている方、シングルマザーとして子育てをしている方、これまでたくさんの方の支援をしてきました。皆さんが苦しみから立ち上がって幸せになり、ありがとうと言ってもらえた時は最高の喜びを感じます。
あとは、やっぱり人との出会いですね。訪問先の方に、「来てくれると元気が出るよ」と喜んでいただけると嬉しいです。でも逆もあって、私がしんどいなあと思った時に、話を聞いてもらったこともあるんです。人生を重ねた方に寄り添ってもらい、とてもいい時間を過ごすことができました。このように民生委員・児童委員である私自身も、地域の方に支えてもらっているんですよ。この活動を一言で言うと、まさに「持ちつ持たれつ」。他の人が経験できないことや、委員をやっていなければ出会うことのできなかった皆さんとのつながりもできる、これが民生委員・児童委員の醍醐味だと思います。
担い手が不足している問題もありますね。
担い手の確保は難しい状況です。民生委員・児童委員の活動は多岐にわたるので、最初は大変だと感じると思います。しかし、1期や2期で全てを分かりこなすことは難しいですし、私自身も、最初の頃は分からないことばかりで、長くは務められないだろうと思っていましたから。でも、ある程度地域の人の様子をキャッチできるようになれば、訪問頻度や関わり方を上手く調整できるようになり、目的も捉えられるようになります。さらに人間関係ができてくると、「〇〇さん、最近ずっと家におってんみたいよ」などの地域の情報も自然に集まるようになるんですよ。地道な活動で積み上げたこのつながりは、私の大きな財産です。もちろん、委員同士、地域包括支援センター、社協の皆さんとのつながりもあるので、課題を共有しながら助け合って活動ができると思います。
最後に、今後の抱負を教えてください。

私が取り組んでいる活動についてお話しましたが、これらは全て「あったかいつながりづくり」に集約できます。誰もが安心して住み慣れた地域に暮らし続けられるよう、すぐ側の人とつながり、仲良く愛情を持って助け合うことが何より大切だと思っています。民生委員・児童委員として、「あったかいつながり」を府中市中に広めていきたいです。
おわりに
高齢者や障害がある人、子育てや介護をしている人などが、周囲に相談できず孤立してしまうケースが近年増えています。住み慣れた地域で誰もが安心して暮らしていくためには、住民同士の身近な助け合い・支え合いが不可欠ですが、高齢化・人口減少などが進む中、それらも困難になりつつあります。
民生委員・児童委員の活動を理解して、あなたも関わってみませんか?
広報ふちゅう10月号の特集では、民生委員・児童委員の活動を紹介しています。ぜひそちらもご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 総務課
広報統計係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9131(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450




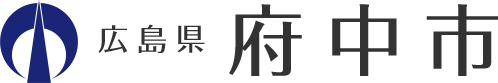




更新日:2023年10月01日