若葉家具 井上社長に聞く「ものづくりのまち府中」の魅力 前編

「ものづくりのまち府中」のなかでも府中家具と言えば代表的なキラーコンテンツ。誰もが知っている府中ブランドの代表選手です。良い物へのこだわり、伝統の技術、職人の技について、楽しい話が聞ける。そう考え伺ったのは若葉家具株式会社代表取締役社長の井上隆雄氏。
ところが、井上社長から聞くのは、どちらかというと楽観視できない現状や危機感、そして今までにない取り組みに関するお話で…。
井上社長にインタビュー
まずは若葉家具の歴史について教えてください。

若葉家具のショールーム外観
創業は私の祖父です。元々は、布団を入れる夜具入れや指物などをつくる木工の職人でした。戦後、府中が婚礼家具セットで躍進した時代に、二代目である父の時代から婚礼箪笥の開発を始めました。府中家具というブランドに乗りながら業績を伸ばし、府中家具メーカーとしての軸ができたのが先代の時代です。
しかしその後、私が府中市に戻ってくる頃には、住宅事情の変化などにより、婚礼家具の需要は激減していました。そんな中、次の手を打たなければいけないということで、箪笥に変わるものづくりを始めたんです。
婚礼箪笥からの切り替えには、業界全体がかなり苦労しました。切り替えが上手くいかず、事業を辞められたところもあります。私たちも、テーブルやイスを作って営業に行くと「府中は箪笥は得意だけど、他の製品は大丈夫なのか」と言われることもしばしば。電気屋さんが車を作って売っている。極端ですが、そのくらいの目で見られていたんですよね。

若葉家具のショールーム
そんな中、10数年前に家具デザイナーの小泉誠さんと出会ったことをきっかけに、生活家具ブランド「kitoki(きとき)」を立ち上げ、自然環境に配慮した素材を用いた、デザイン性が高く、今の生活に合う家具づくりを始めました。府中家具のブランドを生かしながらも、自分たちの名前で発信をしたいという思いから、府中家具でも、若葉家具でもなく、「kitoki」というブランド名を表に出していったんですね。そうすると、製品を評価し、まずブランド自体に興味を持ってくれる人が増えました。そしてあとから若葉家具の製品だと知り、あの箪笥の!となるんですよね。その頃からやっと、私たちの製品が認められ始めたのではないかと思います。
ちょうど10年前には、ショールームのリフォームを行いました。メーカーショールームは敷居が高いというイメージがある中、皆さんが来やすいよう店をオープンにし、小物なども入れショップ化をしました。
話せば長くなってしまうのですが、試行錯誤しながら、時代の変化に対応した新しい製品の開発を今日まで続けてきたわけです。
府中家具といえば一大ブランドですよね?

井上隆雄社長
「府中家具と言えば箪笥」のイメージから変わっておらず、今何をつくり、どんな取り組みをしているかが打ち出せてないのが、業界全体の一つの問題だと思っています。中には、府中家具自体を知らない人もたくさんいるんですよね。知らないということは、福岡県大川市や岐阜県飛騨高山市、北海道旭川市などの他の産地と戦うための土俵にすら乗っていないということなんですよね。
府中家具の箪笥の技術は、やはり当時は秀でたものがあったと思います。「隙間がなくてくるいがない」という強みは、引き出しなどで力を発揮します。しかし、時代とつくるものが変わった今、その強みを発揮できなくなっているんですね。当時の技術は今も受け継いでいますが、今までのように複雑でこだわったものをつくれば売れるという時代でもないので、一般的な人の見方や周りの産地との技術の差はなくなりつつあると思っています。
その中で、他の産地と比べて何が足りないかと言うと、「発信」や「訴求力」だと思います。生活の多様化や競合の躍進など選ぶ側の価値観も変わってきている中、もちろん家具自体もこだわりを持って作っていますが、ただモノをつくるだけの時代ではなくなり、コトやイミを世の中に伝えていくことが重要になっています。それが、私たちの目指す暮らしに沿うということだとも思っています。
隆盛を極めた時代もやはり府中家具の良さを知ってもらう努力があってこそだったはずです。もう一度府中家具を見てもらう、知ってもらうために、今の時代に合った提案やアピールの仕方を考える時期に来ているように思います。
お話は後編へ続きます。下記リンク先からご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 総務課
広報統計係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9131(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450




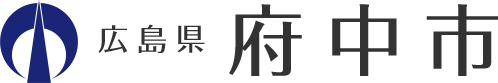




更新日:2023年06月02日